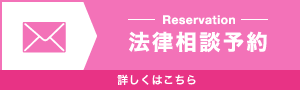債務整理
過払い金についてまず知っておくべき3つのこと
「過払い金」というお金をよく聞くけど、どういう意味なのかイマイチわからない、「過払い金」を自分が請求できるのか知りたい、という方も多いのではないでしょうか。
本記事では「過払い金」について最低限知っておきたい知識についてまとめました。
過払い金とは
(1)なぜお金を払い過ぎたのか?
「過払い金」は、文字通り払い過ぎてしまったお金です。「過払い金返還請求」とは、払い過ぎたお金を返してもらうことです。では、何故、お金を払い過ぎてしまったのでしょうか?
「過払い金」を理解するためには、「利息制限法」、「出資法」、旧「貸金業法」という3つの法律について説明しなくてはなりません。
(2)利息制限法
利息制限法は、貸金における利息の利率を規制する法律です。貸付の元金に応じて、元金10万円未満は年20%、元金10万円以上100万円未満は年18%、元金100万円以上は年15%という三種類の利率を定めています。貸金契約で利息制限法の利率を超える利息を定めても無効であり、その支払義務はありません。しかし、利息制限法には罰則規定がなく違反をしても刑罰を受けないのです。
(3)出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)
刑罰を定めていない利息制限法のかわりに、刑罰をもって高い金利を禁止している法律が出資法です。ところが、禁止されるのは年40.04%(2000年6月まで)、年29.2%(2006年6月まで)という高い利率を超える場合でした。つまり利息制限法に違反しても、それをはるかに超える高利に至っていなければ刑罰を受けなかったのです。
この範囲の金利を、利息制限法違反という意味で「白」ではないが、出資法の刑罰を受けないという意味で「黒」でもないとして、「グレーゾーン金利」と呼んでいました。
貸金業者はこのグレーゾーンの範囲内で利息制限法に違反する高利の利息を取り立てていました。
(4)旧貸金業法(貸金業の規制等に関する法律)
もっとも、貸主に刑罰が適用されないといっても、借主は、利息制限法に違反する利息を支払う義務はありませんから、支払い過ぎた利息(超過利息)は返還を請求できるはずです。
ところが貸金業者は受け取った超過利息を返還しなくてもよいとする法律が存在していたのです。それが旧貸金業法43条「みなし弁済」規定です。
この法律は利息制限法違反の利息でも、債務者の任意による支払いならば、貸金業者が借主に法定の書類を交付していること等を条件として、有効な利息の弁済とみなして、貸金業者は超過利息を返済しなくてもよいと定めていたのです。もちろん、これは貸金業界の利益を守るための法律でした。
(5)グレーゾーン金利とみなし弁済規定が廃止される
しかし、貸金業者による「肝臓を売ってでも返済しろ!」などの過酷な取り立て行為による借主の自殺や一家離散などの被害が深刻な問題となって報道されるにいたり、世論は商工ローンや消費者金融のあり方に厳しい目を向けるようになりました。
平成18(2006)年1月13日、最高裁判所は「みなし弁済」規定を適用する条件を厳しく制限する判決を下しました。これにより、事実上、貸金業者は超過利息を返還しなくてはならなくなりました。
2010年6月、出資法の上限金利と利息制限法の金利は同じく上限年利20%とされてグレーゾーンはなくなりました。2010年6月、貸金業法のみなし弁済規定も廃止されました。
【調査方法】過払い金が発生しているかどうか
(1)貸金業者に取引履歴を開示させる
取引期間が長期にわたるときには、借主の手元にある資料やその記憶だけでは、すべての取引を正確に再現しきれません。
そこで、貸金業者に対し「取引履歴」の開示を求めます。貸金業法によって貸金業者は取引履歴の開示義務を負担していますから、多くの場合は、素直に全ての取引履歴を開示してもらうことができます。
ただし、中には開示請求に応じなかったり、わざと一部しか開示しない業者も存在します。このような場合には、貸金業者の監督官庁である各地方財務局や都道府県金融課などに貸金業法違反であることを告発し、行政指導や処分を求めることができます。
(2)取引履歴に基づき引き直し計算を行う
全取引経過が判明したら、利息制限法の利率に従った引直し計算を行います。引直し計算は複雑なので、電卓で計算することは手間がかかりすぎて現実的ではありません。インターネットなどで専用のソフトを無料配布しているので利用しましょう。
(3)貸金業者に過払い金返還請求を行い、交渉をする
過払い金返還請求の有無と金額が判明したら、貸金業者に対して内容証明郵便の書面をもって返還を請求した後、相手方と交渉を開始する流れとなります。
【時効について】現在借金中なのか完済後なのかで気を付けるべき
(1)過払い金返還請求は10年で時効消滅する
引き直し計算によって過払い金が発生していることが分かってもそれだけで安心することはできません。過払い金返還請求権には10年の消滅時効があるからです。過払い金返還請求権を行使できるときから10年が経過してしまえば、時効によって権利を行使することはできなくなってしまうのです。
(2)過払い金返還請求の消滅時効の起算点は?
10年という消滅時効期間は、いつが起算点になるのでしょうか。
最高裁判所は、過払い金返還請求権の消滅時効は「特段の事情がない限り、同取引が終了した時点から進行する」と判示しました(平成21年1月22日判決)。
「取引が終了した時点」とはいつかが、さらに問題となります。
この点は、一応、次のように考えることができます。
・全額を完済し終えている場合は、完済した日 ・まだ完済していない場合は、最後のお金の出入金(借り入れ又は返済)があった日
(3)最後に返済した日から10年経っているときは諦めるべきなのか?
では、全額を返済した日からすでに10年経ってしまっていたときは、もはや諦めるべきなのでしょうか?
いいえ、諦めるべきではありません。
貸金業者との金銭貸借は、最初に基本契約が結ばれ、一定の与信枠(借入可能額)の中で、借り入れと返済を繰り返してゆく仕組みです。そこで約定にしたがって完済をしていても基本契約が継続していれば、取引は終了していないと理解する余地があるのです。
実際に、最後の返済がなされた後も、基本契約が継続している限り取引は終了はしておらず時効が進行しないとする高裁判決があります(広島高裁平成21年9月28日判決)。したがって、完済から10年を経過していても返還を求めることができる可能性があるのです。あきらめずに、過払い金返還請求に実績のある専門家に相談しましょう。
まとめ
過払い金返還請求は時効の問題ひとつをとっても、法的な議論の激しい分野ですので、この分野で経験と実績のある弁護士に相談、依頼することが大切です。
何かお悩み事がございましたら、お気軽にご相談ください。
東京大学法学部司法学科卒業。最高裁判所司法研修所修了後、裁判官に任官し、横浜地方裁判所、名古屋地方裁判所家庭裁判所豊橋支部、横浜地方裁判所家庭裁判所川崎支部判事補、東京地方裁判所家庭裁判所八王子支部、浦和家庭裁判所、水戸地方裁判所家庭裁判所土浦支部、静岡地方裁判所浜松支部判事。退官後、弁護士法人はるか栃木支部栃木宇都宮法律事務所勤務。
裁判官時代は、主に家事事件(離婚・財産分与・親権・面会交流・遺産分割・遺言)等を担当した。 専門書の執筆も多く、 古典・小説を愛し、知識も豊富である。 短歌も詠み歌歴30年という趣味も持つ。栃木県弁護士会では総務委員会に加入している。
関連記事
-

過払い金返還請求にかかる弁護士費用について知っておくべき3つのこと
「過払い金」というお金をよく聞くけど、どういう意味なのかイマイチわからない、「過払い金」を自分が請求...
2018/09/20
-

過払い金返還請求に強い弁護士・法律事務所を選ぶために必要な3つのこと
「過払い金」というお金をよく聞くけど、どういう意味なのかイマイチわからない、「過払い金」を自分が請求...
2018/09/18
-

過払い金の意味と過払い金が発生する理由
「過払い金」というお金をよく聞くけど、どういう意味なのかイマイチわからない、「過払い金」を自分が請求...
2018/09/13
-

過払い金返還請求を弁護士に依頼するメリットとデメリット
「過払い金」というお金をよく聞くけど、どういう意味なのかイマイチわからない、「過払い金」を自分が請求...
2018/09/12
 日本語
日本語  English
English