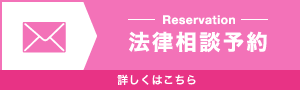不動産・相続
【弁護士の談義】建築請負代金債権の確保と完成建物の所有権の帰属
建築請負代金債権の確保と完成建物の所有権の帰属について述べよ。
目次
1.はじめに
わが民法は、建築請負工事代金債権の確保のために法定担保物権として不動産工事の先取特権 (民三二七条、なお、エ 事が修繕の場合は、民三二六条の不動産保存の先取特権の対象となる)を設けたが、この不動産工事及び不動産保存の各先取特権は、極端に厳格な登記要件が災いしてほとんど利用されていないというのが実情である。
このような状況において、実質的に請負人建築業者の請負工事代金債権の確保に役立ってきたのが、請負人が材料を提供した場合の新築完成建物の所有権を請負人に原始的に帰属させるという学説及び判例実務であったが、最近、 右完成建物の請負人原始帰属説の通説的地位は、学説上はもとより判例実務上も反対説の台頭により揺らぎつつある といわれている。
そこで、本稿では、建築請負工事代金債権の確保をめぐって、不動産工事の先取特権の成立要件・効力・問題点、完成建物の所有権の帰属、所有権留保特約の効力に関する判例・学説の今日的状況について若干検討することとする。
2.不動産工事の先取特権
1 不動産工事の先取特権の意義
不動産工事の先取特権は、民法が工事業者の請負工事代金債権確保のために用意した最もオーソドックスな法的手段―法定担保物権―であって、その立法趣旨は、工事業者の請負工事代金債権の保護と公平の原則にある。
けだし、工事業者の施行した工事によって新たに建設された不動産が注文者の財産に加わり、もしくは既存の不動産の価値が増加したことになるから、工事代金債権について、注文者の所有に帰した工事による増加価値分の上にエ事業者のために先取特権を認めるのが公平の観念に適うからである。
もっとも、不動産工事の先取特権の効力を保全するためには、後述のとおり工事開始前にその費用の予算額を登記するという極めて実行困難な規定 (民三三八条1項)が置かれているうえ、この先取特権の登記をすることは事実上注文者の資力に対する不信の念を表明するものと受け取られかねず、注文者の意向を損なうおそれがあるところから、こ の先取特権の登記はほとんど行われていないというのが実情である。
2 不動産工事の先取特権の被担保債権
(一)債権者 ⑴ 不動産工事の先取特権を有する債権者は、工匠・技師及び請負人である。
ここに、工匠とは、大工・左官・屋根職人・鳶職・植木職人等自ら不動産工事に従事する者、技師とは、工事の設 計・測量・監督をする者、請負人とは、注文者より一定の報酬を受けて工事の完成を約する者(民六三二条)である。
この先取特権の特殊強力な効力からみて、これら工匠・技師及び請負人は制限的列挙であって、これら以外の者 (例えば工事材料を供給した建築資材業者)は、たとえ不動産工事に関する債権を有しても、この先取特権を取得することができない。
⑵ この先取特権を有する者は、直接に不動産の所有者(注文者)との間で工事契約をした者に限られ、かかる者 から更に雇われた工匠・技師・あるいは下請負人は、直接に不動産所有者 (注文者)に対して債権を有する者でない から、この先取特権を有しない。
もっとも、下請負人らは、債権者代位権(民四二三条)に基づいて請負人の有する債権を代位行使しうるので、その限度で請負人の先取特権を行使しうることになる。
(二)不動産工事 不動産工事とは、土地の埋立・開墾・整地・擁壁築造・耕地整理・建物の新築・増築・改築等 である。
建物の修繕のための工事代金債権は、後記二5(一)のとおり不動産の保存行為による債権として民法二六条の不動 産保存の先取特権による保護の対象となるが、建物の改築と大修繕との境界は、抽象的・観念的にはともかくとして、現実には必ずしも明確ではなく、個々具体的なケースにつき社会通念に従って判断するほかはない。
なお、建物新築工事の場合、なるほど工事開始時には、不動産は存在しないが、制度の趣旨から考えると「不動産ニ関シテ為シタル」工事と解すべきことは当然である。
(三)被担保債権の範囲 実際の工事費用が登記された予算額を超過しても、超過額については不動産工事の先取特権によって担保されず(民三三八条一項但書)、無担保の一般債権となり、他方、逆に実際の工事費用が登記された予算額に達しなかったときは、実際の工事費用の範囲でこの先取特権が成立することになる。
3 不動産工事の先取特権の目的物
この先取特権は、工事を加えられた不動産につき工事によって生じた不動産の増価額が現存する場合に限り、その増価額の上にのみ存在する(民三二七条二項)。
したがって、不動産工事費用が不動産の現存増価額を下廻るときは、その全額がこの先取特権により担保されるが、逆に工事費用が現存増価額を上廻るときは、現存増価額の範囲に限りこの先取特権により担保され、これを越える部分は無担保の一般債権となる。
そこで、前記2(三)を考えあわせると、結局、不動産工事の先取特権者としては、登記された工事費用予算額、実際の工事費用額、現存増価額の三者のうち最も少ない額の範囲でこの先取特権を行使できることになる。
不動産增価額現存の基準時は、先取特権行使時であるから、工事後日時が経過して工事直後にはいったん工事により増加した価値が減少して元の不動産の価額と同額となれば、この先取特権を行使できないことになる。
不動産の増価額が現存するか否か、その増価額がいかほどになるかについては、不動産工事の先取特権者、債務者のみならず他の担保物権者や一般債権者の利害に大きく影響するところから、競売手続における配当加入時に裁判所が選任した鑑定人に評価させる(民三三八条二項)ことになっている。
4 不動産工事の先取特権の登記
(一) 特殊な登記を必要とした趣旨 民法三三八条が不動産工事の先取特権につき工事開始前の費用予算額の登記履践という厳格な要件を定めたのは、法律上当然に生ずる法定担保物権をできるだけ速やかに公示して不動産取引の 安全を図るのが望ましいこと、とりわけ、不動産工事の先取特権はその額も大きく、しかも所定の登記がなされると先順位で登記された抵当権などに優先して配当を受けることができるため、工事完了まではいつでも登記ができるとすると、独立の不動産となった後の未完成の建物に抵当権を設定し登記を了した者が、その後に登記された不動産エ事の先取特権によって優先されて思わぬ損害を被ることがあるからである、といわれている。
しかしながら、反面、工事着手前事前に工事予算額を登記することは事実上困難で、工事業者にとってこの不動産工事の先取特権は実用性に乏しい制度になっており、立法論的に批判が多いところである。
(二)不動産工事の先取特権の登記時期 ⑴ 民法三三八条一項によれば、不動産工事の先取特権は、「工事ヲ始ムル前」にその費用の予算額を登記すべきものとされており、この「工事ヲ始ムル前」とは、工事着手前であって、工事着手後になされた不動産工事の先取特権の登記は全く無効である(登記後の工事分についても有効になるわけではない)というのが古くからの通説・判例(大判大正六年二月九日民録二三韓二四四頁ほか)であり、最近の下級審判例、例えば浦和地判 昭和五八年二月二二日 (判夕四九八号一五五頁)、東京高判昭和六〇年一一月二一日 (金融法務一一一九号四六頁)も依然として登記時期の制約を厳格に解している。
建物新築の場合に、工事着手後になって棟上後の費用について不動産保存の先取特権の登記をしても、建物新築工事は着工から完成までが一連の工事であるから棟上後だけを切り離して不動産の保存とすることはできず、このような不動産保存の先取特権の登記は無効であるというのが判例(大判明治四三年10月1八日民録一六輯六九九頁)である。
⑵ しかしながら、最近の学説は、一致して、不動産工事の先取特権の登記時期を工事着手前に限るのは実質的に 工事業者に著しい困難を強いるので妥当でないと批判し、立法論としては工事着手後にも登記を認め、他の抵当権等との優劣は純然たる対抗要件の問題として処理すべきものであるとしている。
さらに、立法論にとどまらず、解釈論としても不動産工事の先取特権の登記時期の制約をその登記を対抗すべき相手方によって区別してある程度弾力的かつ相対的に解釈することが西原教授(注釈民法⑻220頁)によって提唱されているが、未だ大方の支持を得るには至っていない。
(三)不動産工事の先取特権の登記手続 不動産工事の先取特権の登記手続については、不動産登記法一三六条以下に規定されており、ことに建物新築の場合には建物の登記はもとより建物自体が未だ存在しないところから、その手続はかなり面倒で、細かい技術的問題になるのでここでは省略するが、青林書院刊注解不動産法第2巻「建築・請負」所収の民法三三八条の注釈 【太田執筆】を参照されたい。
(四)不動産工事の先取特権登記の効力 ⑴ 登記による効力保存の意味民法三三八条は、不動産工事の先取特権につき工事着手前に工事費用の予算額を「登記スルニ因リテ其効力ヲ保存ス」と規定しているのでその意味が問題となる。
かつての通説は、この先取特権の登記は効力要件で、所定の登記をしない限り先取特権は当事者間でも効力がなく、競売申立てもできないとするものであったが、その後次第に、登記は一般の原則どおり対第三者対抗要件にすぎ ず、当事者間(先取特権者と債務者=不動産所有者間)では登記なしでも先取特権は生じ競売申立てもできるが、ただ優先権が生じないにすぎないと解する説が有力となり同旨の高裁判例も存在した。
しかし、民事執行法一八一条一項は、一般先取特権以外の不動産担保物権による担保権実行のための競売申立てについて、担保権の存在を証する確定判決の謄本(同項一号)、担保権の存在を証する公証人の作成した公正証書の謄本(同項二号)、担保権の登記(仮登記を除く)のされている登記簿の謄本(同項三号)のいずれかの提出を不動産競売開始の要 件としており、不動産工事の先取特権に関しては、三号の登記簿の謄本以外のものの存在は実質的には考えられないため、先取特権者と債務者の当事者間でも登記がなされていない限り(もとより同項一号の確定判決の謄本や二号の公正証菩の膨 本があれば別論)競売の申立てもできないことになったといえよう。
⑵ 登記の効力 所定の要件に従って不動産工事の先取特権の登記がなされると、この先取特権者は、登記の先選後にかかわらず、不動産保存の先取特権(民三三一条一項・三二五条一号)には後れるが、共益費用以外の一般先取特権(民三三九条二項)、不動産売買の先取特権(民三三一条一項・三二五条 三号)、抵当権(民三三九条)、不動産質権(民三六一条・三三九条)に優先して競売代金の配当を受けることができる。
5 不動産保存の先取特権
(一) 不動産保存の先取特権の意義 建築請負工事が建物の改築に至らず単なる修繕に当るときは、その工事代金債権は、不動産の保存費として不動産保存の先取特権(民三二六条)による保護の対象となる。
不動産保存の先取特権の立法趣旨は、不動産の滅失毀損や価格減少を防止するための保存行為が他の債権者にとっても共通の担保の維持をもたすらことに着眼して、保存者及び他の債権者間の公平を図ることにある。
(二) 不動産保存の先取特権の目的物 不動産保存の先取特権の目的物は、保存された不動産であるが、抵当権の規定が準用される(民三四一条)結果、先取特権成立後の付加物 (民三七〇条)、差押後に生じた天然果実(民三七一条)も目的物に含まれることに注意しなければならない。
(三) 不動産保存の先取特権の登記 民法は、不動産保存の先取特権の登記についても、物権法の一般原則によらないで、その登記をなすべき時期を保存行為直後に限定しているが、その趣旨は、法定担保物権である不動産保存の先取特権をなるべく速やかに公示してその存在を第三者に知らせて不動産取引の安全に資することのほか、不動産保存の先取特権により担保される債権が高額となりうることにあるといわれている。
民法三三七条によると、不動産保存の先取特権は、「保存行為完了ノ後直チニ(筆者注―保存費用の)登記ヲ為スニ因 リテ其効力ヲ保存ス」るとされており、ここに「直チニ」とは、通説によれば遅滞なくの意味であるとされ、他方、 少数説として第三者が抵当権や質権を設定する前ならいつでもよいという見解もあるが、この説は立法論は別として解釈論としては未だ大方の支持を得るには至っていない。
(四)不動産保存の先取特権の効力 所定の要件に従って不動産保存の先取特権の登記がなされると、この先取特権者は、登記の先後にかかわらず、共益費用以外の一般先取特権(民三二九条二項)、不動産工事の先取特権(民三ミ一条 一項・三二五条二号)、不動産売買の先取特権(民三三一条一項・三二五条三号)、抵当権(民三三九条)、不動産質権(民三六一条・三 三九条)に優先して、つまり実質的に最優先で競売代金の配当を受けることができる。
3.完成建物の所有権の帰属
建築請負契約における完成建物の所有権の帰属については、かつては、判例・学說とも一致して、注文者と請負人のいずれが主要な材料を提供したかによって区別して、主要な材料の提供者をもって所有者としてきたのであるが、 近年、学説においては、主要な材料の提供者がいずれであるかを問わず、常に注文者が完成建物の所有権を原始的に取得するとの考え方が有力化してきており、判例も請負人が主要な材料を提供して工事を完成させても注文者が請負代金を完済した場合には、黙示の特約を認めることにより建物の注文者への帰属を認め、この限りにおいて実質的に 最近の有力学說と同じ結論を認めるに至っているが、この問題の帰趨は本稿の目的とする請負工事代金債権の確保の方法とも関連してくるところである。
そこで、以下の考察においては、下請負のない場合、下請負のある場合、請負人が中途で工事を中止した場合に分けて現在の判例・学說の状況を検討することとする。
1 下請負のない場合
(一) 注文者が主として材料を提供した場合 ⑴ 判例 この場合、判例は、とくに理由を説明することなく当 初から一貫して完成建物の所有権は当然原始的に注文者に帰属するものとしてきたし、また、注文者が材料そのものではなくその購入代金を請負人に交付した場合にも材料を提供した場合と同様に完成建物の所有権は当然原始的に注文者に帰属するものとしてきた。
⑵ 学説 学説もこの場合、通常の当事者間の意思の合理的推測などを根拠に完成建物の所有権は当然原始的に注文者に帰属するとしており、異説はないようである。
(二) 請負人が主として材料を提供した場合 ⑴判例 ① 原則的な場合 請負人が主として材料を提供して建物を完成させた場合、判例(例えば、大判大正三年一二月二六日民録二O輯 一二〇八頁)は、材料・労力とる請負人の供給したものであることに加え、引渡しによって債務が完了して報酬請求権が発生し危険負担も移ること、わが法制上建物 は土地とは別個の独立の不動産であること等を根拠として、完成建物の所有権は明示もしくは黙示の合意 (特約)がない限りいったん請負人に帰属し、引渡しによって注文者に移転するとしている。
② 特約がある場合 請負人が主として材料を提供して建物を完成させた場合でも、もとより、注文者・請負人間で建物の完成・引渡しに先立って建物の所有権を原始的に注文者に帰属させる旨の合意がなされれば、これに従うというのが判例(大判大正五年一二月一三日民録二二輯二四一七頁)である。
③ 工事代金を完済した場合 請負人が主として材料を提供して建物を完成させた場合でも、注文者が建物完成前に工事代金全額を完済した場合には、特別な事情がない限り当事者間に工事完成と同時に建物を注文者の所有にする旨の暗黙の合意があったとみるのが判例(大判昭和一八年七月二〇日民集二三巻六六〇頁)であり、右暗黙の合意を認める根拠は建築材料を注文者が提供した場合と同視できることにあるようである。
④ 工事代金の大部分を支払った場合 請負人が主として材料を提供して建物を完成させた場合について、注文者が建物完成前に工事代金全額とまでいかなくとも、大部分を支払った場合に、建物の完成時に注文者に所有権を帰 属させる合意があったと認めた判例(例えば、最判昭和四六年三月五日判時六二八号四八頁は、建売住宅六棟の注文者である建売業者から 請負人に対し代金支払いのため約束手形後に不渡りとなったが交付された際に建築確認通知書が注文者に交付され、入居者の決まった三棟だけ引渡しがなされて残りの引渡し未了の三棟の所有権が問題となった事案につき建物完成時全六棟の所有権を注文者に帰属させる旨の合意があったものと認めたもの、最判昭和四四年九月一二日判時五七二号二五頁は、棟上げ時までに全工事代金の半額以上を支払い、なお工事の進行に応じ残代金の支払いをしてきた事案につき引渡しを待たず建物完成と同時に建物所有権が原始的に注文者に帰属するとしたもの)が見られる。
⑵ 学説 ① 請負人帰属説 かつて、通説は、請負人が主として材料を提供して建物を完成させた場合、当事者の意思の合理的推測等を根拠として、前記大正三年大判と同様に完成建物の所有権は、一旦請負人に帰属し、原 則として引渡しによって注文者に移転すると解していた(鳩山、末弘、我妻、末川、石田 (文)、浅井の各教授ら、なお最近では米倉 教授)。
もっとも、当事者間の特約により引渡しを待たず建物の完成と同時に原始的に所有権が注文者に帰属する旨定める ことは有効で、工事代金全額を支払った場合にはかような特約があるものと推定すべきである (我妻教授)とも説かれていた。
② 注文者帰属説 これに対し、最近では、注文者のために注文者に所有されるべき建物を建築するという当事者意思の分析、工事代金の大部分が工事完成前に分割払いされるという支払方法の実態、建物の敷地利用権の関係、不動産工事先取特権の規定様式、下請負との関係、請負人の工事代金確保のための他の手段の存在、建築確認申請及 び保存登記名義人が多くの場合注文者であるという実態、請負人に建築建物の処分権を与えることの不当性等を根拠として、たとえ請負人が主として材料を提供して建物を完成させた場合であっても、完成建物の所有権は引渡しを待たず原始的に注文者に帰属するという説が圧倒的多数をしめている(加藤、来栖、星野、柚木、吉原、石外、石田(喜)、内山、 鈴木、石田(穣)、坂本の各教授、後藤判事)。
2 下請負人が材料を提供して建物を完成させた場合
(一) 判例 ⑴ 下請負人帰属説 一括下請負がなされ、下請負人が材料を提供して建物を完成させた場合にお いて、注文者は元請負人に元請負代金を完済したが、元請負人は下請負人に下請負代金を支払わずに倒産してしまっ たようなときには、前記1(二)⑴の判例理論からは、単純に考えれば、下請負代金が支払われていない以上、注文者も しくは元請負人が下請負人から建物の引渡しを受けていない限り、下請負人に所有権が留まるはずで、元請負人に元 請負代金を完済したにすぎない注文者に完成建物の所有権が帰属するという結論を出すことは困難なように思われ、 古くはその趣旨の判例(大判大正四年10月11日民録二一輯一七四六頁)もあった。
⑵ 注文者帰属説 しかしながら、前記下請負人帰属説の結論は、元請負代金を完済しながら何ら自己の関知しない下請負代金の未払いのいわば「とばっちり」を受ける注文者の立場を考えると如何にも落ち着きの良くないものである。
そこで、このような場合につき、さしたる理論的説明をすることなく個別的諸事情を総合して建物完成と同時にその所有権が注文者に帰属したと認めたもの(東京地判昭和五七年七月九日判時10六三号一八九頁)、下請負人を元請負人の一種の履行代用者とみて下請負人と元請負人とを一群として捉えて建物完成と同時にその所有権が注文者に帰属したと認めたもの (仙台高決昭和五九年九月四日判タ五四二号二二〇頁)がある。
なお、元請負代金、下請負代金がいずれも工事完成前に完済されている場合に、建築された建物が独立の不動産となると同時にその所有権を注文者に原始的に帰属させる旨の暗黙の合意が存したものと認めた判例(東京高判昭和五九年一〇月三〇日判時一二三九号四二頁)もあるが、これは前記112の判例理論の当然の帰結にすぎない。
⑶ 権利濫用の法理により注文者を保護したもの下請負人が材料全部を提供して完成させた建物につき、元請負人がこれを注文者に引き渡し、代金全額の支払いを受けている場合には、下請負人が注文者に対し下請負工事代金 の不払いを根拠に自己に所有権ないし占有権があることを理由として建物所有権確認及び明渡しの請求をすることは信義則、権利濫用の法理に照らして許されないとした判例(東京高判昭和五八年七月二八日判時一〇八七号六七頁)、下請負人が 材料労力全部を提供して一括下請負により建築した建物につき、元請負人に代金全額は支払ったものの元請負人が下 請負人に振り出した約束手形の決済がなされていない事実を知りうる立場にあった注文者が建物の現実の占有は取得せず表示登記・保存登記をなしたうえ住宅ローン会社に抵当権設定登記を経由した場合に、下請負人から注文者に対し右建物の所有権の確認・保存登記の抹消登記手続、ローン会社に対し抵当権設定登記の抹消登記手続をするのは、注文者に右建物の所有権を帰属させるべき三者間の合意があったと同視しうる特段の事情が認められないとして下請 負人の所有権の確認の限度で認容し、注文者の保存登記及びローン会社の抵当権設定登記の各抹消登記手続請求は権利濫用であって許されないとして棄却した判例(東京地判昭和六一年五月二七日判時一二三九号七一頁)がある。
⑷ 所有権留保特約のある場合 下請負関係のあるプレハブ建物建築請負契約において、注文者は元請負人に元 請負代金を完済したのに元請負人は下請負人に下請負代金を支払わず、一方、建物は既に下請負人から元請負人を経 て注文者に引き渡されたという場合につき、下請負人であるプレハブ会社と元請負人との間の所有権留保特約条項に文字通りの意味での効力を否定して引渡しにより下請負人から元請負人へ所有権が移転する黙示的合意があったとし て注文者への完成建物所有権の帰属を認めた判例(東京高判昭和五四年四月一九日判時九三四号五六頁)、所有権留保特約の効力は一応肯定したものの、元請負人が下請負人の仲介人ないし代理人的立場にあり、建物が下請負人から元請負人を 経て注文者に引き渡され保存登記も了されていることを考慮して、下請負人が注文者に対し所有権留保特約に基づき建物引渡請求をすることは、下請負人が自ら負うべき下請負代金の不払いのリスクを注文者に転嫁するもので、権利 認 濫用に当り許されないとした判例 (大阪高判昭和五六年五月二九日判時一〇一六号七二頁)等がみられる。
これらの判例においては、いずれも下請負人から元請負人に任意に引渡しがなされ、さらに注文者が元請負人から引渡しを受けている場合であるから、所有権留保特約がない限りは従前の判例・通説の立場でも注文者への建物所有権の帰属が認められるケースであるが、このような場合に下請負人・元請負人間で所有権留保特約をしても、元請負代金を完済した注文者との関係では右特約の効力を実質的には認めなかったという意味で、判例の下請負がある場合の注文者保護の強い方針の一斑を示したものといえよう。
(二) 学說ー最近の注文者帰属說 学説は、従来、一括下請負があって下請負人が材料を提供して建物を完成させ、注文者は元請負人に元請負代金を完済したが、元請負人は下請負人に下請負代金を支払っていない場合における完成建物の所有権の帰属について特に論じたものはなかった。
もっとも、従来の通説であった請負人帰属説によれば、一括下請負がある場合には、下請負関係、元請負関係の二段階でそれぞれ引渡し、もしくは請負代金完済がなければ注文者に完成建物の所有権の帰属を認めることはできないということになろう。
しかし、前記(一)⑶の東京高裁昭和五八年七月二八日判決 (判時10八七号六七頁)に対する判例評釈において、滝沢、 鎌田の各教授は、同判決の注文者保護の結論には賛同しながらも、権利濫用の法律構成では注文者に建物所有権した がってその登記名義を取得させられない点で紛争の最終的解決にならないという問題があるとして反対し、下請負人と注文者の間には直接の契約関係は存在しないものの下請負契約の内容自体が元請負契約の存在を予想するものであるところから、下請負人の工事の成果は元請負人を介して当然に注文者に帰属する(滝沢・判評三01号三二頁)、建築請負契約は注文者に新築建物の所有権を取得させる契約であり、下請負人は元請負人の履行補助者ないし履行代行者にすぎないから端的に注文者が原始的に完成建物の所有権を取得すると解すべきである(鎌田・判タ五二二号九五頁)として、注文者帰属説を主張される。
3 請負人が中途で工事を中止した場合
⑴ 判例 未完成建物、建前の所有権帰属 当初の請負人が工事を中途で中止した場合に、注文者が工事中止までに未完成建物、建前の出来高部分以上の請負代金を支払っていたときは、完成建物の場合と同様に当事者間 に暗黙の合意の存在を推認して右未完成建物、建前の所有権が注文者に原始的に帰属すると認めるのが判例(例えば、東京地判昭和三四年二月一七日下級民集一〇巻二号二九六頁)である。
⑵ 注文者側でした残工事と加工の法理の適用 当初の請負人が未だ建物といえるに至らない段階で工事を中止したため、注文者が自らもしくは他の業者に注文して残工事をなし建物を完成した場合には加工の法理を類推適用すべきであるというのが判例で、最判昭和五四年一月二五日(民集三三巻一号二六頁)は、建物の建築工事請負人が建築途上において未だ独立の不動産に至らない建前を築造したままの状態で放置していたのに第三者が材料を供して工事を施して独立の不動産である建物に仕上げた場合において右建物の所有権が何びとに帰属するかは、動産に動産を単純に合させるだけでそこに施される工作の価値を無視してよい場合とは異なり、材料に対して施される工作が特段の価値を有し仕上げられた建物の価値が原材料のそれよりも相当程度増加するような場合に当るから、民法二四三条の動産の附合の規定によるのではなく、むしろ二四六条二項の加工の規定に基づいて決定すべきである旨を判示した。
もっとも、前記の例とは異なり、当初の請負人の工事中止当時未完成建物が既に一応不動産の体をなしていたと認められるときは、当然のことであるが、加工の規定の適用はなく不動産の附合の規定の適用があるというのが判例である。
(二)学説 未完成建物、建前の所有権帰属前記1日の最高裁昭和五四年判決は、請負人が材料を提供して建築を始めた場合に建築途上の不動産となる前段階の動産である建前が請負人の所有であることを前提として論を 進めており、従来の通説もこの結論を疑わなかったようである(もっとも、建前の所有権の帰属につき触れたものはほとんどな い)が、前記最高裁判決の評釈を公にされた石田(穣)、瀬川の各教授は、当事者意思の推測、請負契約の趣旨・実態 等を根拠に建前についても原始的に注文者に帰属する旨主張され、むしろ近時は建築段階の如何を問わず注文者帰属説の方が有力のようである。
⑵ 建前に第三者が続行工事をして建物を完成した場合の完成建物の所有権の帰属 前記(一)⑵の最高裁昭和五四年判決に対しては多くの評釈が公にされたが、いずれも、建築工事という事柄の性質上単なる動産と動産の価格を比較して所有権の帰属を決める動産の附合の規定によるよりも、価格増加のための有用労働(工事)を加味して所有権の帰属を決める加工の規定による方が妥当であるとして概ね判旨に賛意を表している。
もっとも、最近の有力説である完成建物の注文者原始帰属説の考え方に立つならば、もともと建前の所有権も注文 者に帰属しており、これに注文者の命を受けた別の請負人が続行工事を行った場合には、完成建物の所有権は、加工の規定の適用など問題にするまでもなく当然に注文者に帰属する(瀬川・判評二四九号一九頁)と考えるのが筋であろう。
4.所有権留保その他
1 所有権留保
従来の通説・判例であった建築請負契約の完成建物の所有権が原始的に請負人に帰属し、引渡しもしくは代金完済により注文者に移転するとの考え方の根底には、代金全額の支払いを受けていない請負人の工事代金債権の確保を助 けたいという実質的考慮が潜んでいたことが夙に指摘されていたところである。
ところが、最近の有力説が引渡し及び代金支払いの有無を問わず原始的に完成建物の所有権が注文者に帰属するとの考え方をとり、判例も下請負のある事案で注文者が元請負代金を完済したが下請負代金が支払われていない場合につき注文者を保護し実質的に注文者への所有権の帰属を認めるのと変わりない立場をとるようになっているところから、近時、とりわけ下請負人が下請負代金の支払いを確保するため所有権留保の特約を付する例がみられるようである。
(一) 判例 下請負人が元請負人との間で所有権留保の特約をした場合に関する判例として、前記三2(一)⑷でみた、下請負関係のある建築請負契約において、注文者は元請負人に元請負代金を完済したのに元請負人は下請負人に下請負代金を支払わず、一方、建物は既に下請負人から元請負人を経て注文者に引き渡されたという場合につき、下請負人であるプレハブ会社と元請負人との間の所有権留保特約条項に文字通りの意味での効力を否定して引渡しによ り下請負人から元請負人へ所有権が移転する黙示的合意があったとして注文者への完成建物所有権の帰属を認めた前記昭和五四年東京高裁判例と、所有権留保特約の効力は一応肯定したものの、元請負人が下請負人の仲介人ないし代理人的立場にあり建物が下請負人から元請負人を経て注文者に引き渡され保存登記も了されていることを考慮して、 下請負人が注文者に対し所有権留保特約に基づき建物引渡請求をすることは、下請負人が自ら負うべき下請負代金の不払いのリスクを注文者に転嫁するもので、権利濫用に当り許されないとした前記昭和五六年大阪高裁判例がある。
これらの判例のケースは、いずれも下請負人から元請負人に任意に引渡しがなされ、さらに注文者が元請負人から 引渡しを受けている場合であるから、所有権留保特約がない限りは従前の判例・通説の立場でも注文者への建物所有権の帰属が認められるケースであるが、このような場合に下請負人が下請負代金確保のために元請負人との間で所有権留保特約をしても、元請負代金を完済した注文者との関係では右特約の効力が実質的には認められなかったという意味で、判例の下請負がある場合の注文者保護の強い方針の一斑を示すものといえよう。
(二) 学説 学説は、従来、建物建築請負契約において注文者が代金を完済するまで請負人に所有権を留保する旨の特約の効力につき問題意識をもって取り上げたことはなかったが、前記昭和五四年及び昭和五六年の高裁判例を受 けて判例評釈が公にされるに至った。
まず、昭和五四年東京高裁判例を評釈した生熊教授は、所有権留保特約条項は請負代金債権担保のためのものであるから請負人は所有権留保という担保権を取得するにすぎず、完成建物の所有権は建物完成と同時に注文者に原始的に帰属し、所有権留保特約の実質は譲渡担保権設定の合意であり、その旨の登記手続をしなければ第三者 (筆者注―下請負人が元下請負人との間で所有権留保特約をした場合の注文者)に対抗できないとされる(生熊・判夕四一一号五三頁)が、そもそも 原始的注文者帰属説に立つならば、下請負がある場合でも建物の所有権が元請負人を介して原始的に注文者に帰属するはずであるから、元請負人ではなく注文者との間で所有権留保という担保設定契約をしなければ効力がないことになるのではなかろうか。
次に、昭和五六年大阪高裁判例を評釈した滝沢教授は、注文者の事前の書面による承諾を欠く一括下請負を禁じた建設業法二二条の規定に着目して、右承諾を欠く一括下請負が行われた場合には下請負関係を当事者の内部関係に限定して下請負人の所有権留保特約の主張を排斥すべきであり、同条所定の承諾のある一括下請負が行われた場合にも動産において転売授権と所有権留保が両立しがたいのと同様に注文者に所有権を取得させない下請負契約が無意味であることに徹して右一括下請負への承諾の存在の一事をもって所有権留保特約の効力を当然に注文者に主張しうることにはならず、注文者を引き込むためには所有権留保についての注文者の承諾が必要である、また、近時の注文者原 始帰属説によるならば注文者は下請負人による工事の成果を元請負人を介して当然に原始取得するから、注文者と無 関係に所有権を留保することがそもそも不可能になるとされる(滝沢・ジュリ七七〇号-10頁)。
かように、最近の学説によれば、下請負人が下請負代金債権確保のため元請負人との間で所有権留保特約をして も、元請負代金を完済した注文者との関係では、注文者の同意なくして右所有権留保特約の効力を主張し得ないとい うことになり、その実効性は必ずしも大きいものとはいえない。
2 留置権、同時履行の抗弁権
(一)下請負のない場合 請負人が請負工事代金の支払いを受けるまで留置権、同時履行の抗弁権により注文者に対して完成建物 (借地人の地主に対する建物買取請求に基づく留置権と同じく敷地にも及ぶものと解されている)の引渡しを拒むことができ、また、請負工事代金が出来高払方式であるときは出来高に見合った中間金の支払いがない限り工事の続行を拒 否することができることはいうまでもない。
なお、請負人による引渡しがないのに注文者が実力で完成建物を占有してしまったときには、請負人は占有回収の訴えにより建物返還請求をなしうる。
(二) 下請負のある場合 ここでも、下請負がある場合の下請負人の下請負代金のための留置権、同時履行の抗弁権については厄介な問題がある。
単純に考えれば、一括下請負が行われた場合には、注文者と元請負人との間、元請負人と下請負人との間にそれぞれ別個独立の請負契約が存在して、下請負人は元請負人に対する下請負代金債権を担保するために留置権をもって注 文者に対抗しうるように思われるが、しかし、この説では元請負人が下請負人に下請負代金を支払っていない場合に元負代金全額を支払った注文者に二度払いを強いるもので妥当とは思われない。
判例としては、このような下請負がある場合について、元請負代金全額を支払った注文者に二度払いを強いるのは 妥当でないなどとして下請負人の占有権に基づく引渡しの主張を権利濫用として退けた前記三2(一)⑶の昭和五八年東京高裁判決がみられる程度である。
学説としては、このような下請負がある場合について、権利濫用のような一般条項に頼るのでなく、第一に、下請負人は元請負人の履行補助者的地位にあり独立の占有者とみるべきではないこと、第二に、仮りに下請負人に独立の占有者の地位を認めるにしても、下請負代金の支払いは元請負代金の支払後になされるのが一般であり注文者の元請 負代金の支払いと完成建物の引渡しとが同時履行の関係にある以上、下請負人の元請負人への完成建物の引渡義務は下請負代金の支払義務に対して先履行の関係にあること、などを根拠にして、そもそも、下請負人は元請負人に対する下請負代金債権につき留置権、同時履行の抗弁権を有しないもので、結局、下請負人は元請負人に対して出来高払契約においては中間金の支払いがない限り残工事をしないという抗弁のみを下請負代金保全の手段として有するにす ぎない、と解すべきであるとする鎌田教授の見解 (判タ五二二号101頁)がある。
3 下請負代金保全の手段
このように見てくると、下請負がある場合については、元請負人との所有権留保の特約も、下請負代金債権についての留置権、同時履行の抗弁権も注文者との関係では主張しえないもので、いささか下請負人には酷な感もあるが、下請負人はなんといっても専門家でかつ元請負人とは業者同士で注文者と比べれば密接な関係にあり元請負人の経済状態を把握してしかるべき手段を講ずる余地もあること、注文者は一回的な関係であるのに対し下請負人は継続的業務の中で損失回復・平均化の機会もあること、下請負人は出来高払契約の場合中間金の支払いがない限り残工事をしないという抗弁を有するので注文者とも交渉して元請負代金の支払いに立ち会って下請負代金債権を回収すべき手段を講ずる余地もあること、自己の与かり知らない下請負関係のトラブルにより元請負人に請負工事代金全額を支払った注文者に工事代金の二度払いを強いるのは妥当とは思われないこと、に照らして前記判例実務及び近時の学説の動向は妥当なものである。
5.結びにかえて
本稿は、建築請負代金債権の確保とこれに関連する完成建物の所有権の帰属について、不動産工事の先取特権の成立要件・効力・問題点、完成建物の所有権の帰属、所有権留保特約の効力に関する判例・学説の今日的状況について 若干検討してきたわけであるが、これを要約すれば、完成建物の所有権の帰属については注文者保護の配慮の必要性と工事代金が七割がた建物完成前に分割支払われる実態ともあいまって実質的に注文者原始帰属説に近い判例実務上の処理がなされていること、下請負人の下請負代金確保のための所有権留保特約も留置権も元請負人に代金を完済した注文者との関係では注文者保護を重視する判例実務上実効性に乏しいものとなっていること、学説も概ね結論的に は前記判例実務を支持しむしろより進んで下請負関係を含めて注文者原始取得說を徹底する傾向にあること、本来の建築請負代金債権の確保のための法定担保物権である不動産工事の先取特権は異常に厳格な成立要件に災いされてほとんど利用されていないことが指摘され、立法論としては不動産工事の先取特権の成立要件とりわけその登記時期の 制約を緩和して工事着手後にも登記を認め、他の抵当権等との優劣は純然たる対抗要件の問題として処理すべきものとして実際に利用できる制度とする必要があることが指摘されている。

早稲田大学法学部卒業。司法修習終了、ワシントン大学ロースクール修士課程修了、ハーバード大学客員研究員、ブラウン・守谷・帆足・窪田法律事務所パートナー、長浜・山口法律事務所を設立、東京山王法律事務所と改称し、今日に至る。
第一東京弁護士会常議委員、厚生部委員会副委員長・綱紀委員会委員・人権擁護委員会委員・司法制度調査委員会委員・厚生部委員会委員・刑事法制委員会委員・選挙管理委員会委員、日本弁護士連合会通信傍受法組織犯罪対策法に関する拡大理事会委員など。
(元)東京簡易裁判所民事調停委員
(現)日本海運集会所仲裁委員
(現)ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)登録弁護士
(現)日本弁護士連合会中小企業の海外展開支援事業 登録弁護士
東京大学法学部司法学科卒業。最高裁判所司法研修所修了後、裁判官に任官し、横浜地方裁判所、名古屋地方裁判所家庭裁判所豊橋支部、横浜地方裁判所家庭裁判所川崎支部判事補、東京地方裁判所家庭裁判所八王子支部、浦和家庭裁判所、水戸地方裁判所家庭裁判所土浦支部、静岡地方裁判所浜松支部判事。退官後、弁護士法人はるか栃木支部栃木宇都宮法律事務所勤務。
裁判官時代は、主に家事事件(離婚・財産分与・親権・面会交流・遺産分割・遺言)等を担当した。 専門書の執筆も多く、 古典・小説を愛し、知識も豊富である。 短歌も詠み歌歴30年という趣味も持つ。栃木県弁護士会では総務委員会に加入している。
関連記事
-

遺産を相続することになった!ときに最低限知っておきたい必要な手続
建築請負代金債権の確保と完成建物の所有権の帰属について述べよ。  ...
2019/02/20
-

遺産の相続放棄をすべきか?すべきじゃないか?と悩む前に知っておくべきこと
建築請負代金債権の確保と完成建物の所有権の帰属について述べよ。  ...
2019/02/15
-

弁護士がイチから教える遺産相続のために最低限これだけは知っておきたいこと
建築請負代金債権の確保と完成建物の所有権の帰属について述べよ。  ...
2019/02/14
-

相続人である兄弟姉妹が勝手に亡き親の家に住みついた場合の対応法
建築請負代金債権の確保と完成建物の所有権の帰属について述べよ。  ...
2018/10/03
 日本語
日本語