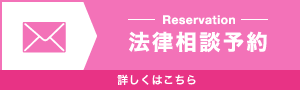離婚
【離婚と財産分与】夫婦の切れ目が財産の切れ目?
離婚と財産分与の方法は似ている
この記事では、配偶者との離婚を検討されている方向けに、財産分与の種類や対象となる財産、財産分与の方法について解説します。
まず知っておきたい財産分与の種類
財産分与には、以下の3種類があります。
(1)清算的財産分与
清算的財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産を清算するもので、財産分与の中核的なものです。財産の名義が誰のものであるか、離婚原因がどちらにあるかかは関係なく、財産分与を請求することが可能です。
(2)扶養的財産分与
扶養的財産分与とは、離婚をすると経済的に困窮してしまう一方のために、他方が生活を支える目的で財産を分与をするものです。病気や経済的に厳しい状況にある配偶者に対して、定期的に一定金額を支払っていくなどの方法がとられます。
(3)慰謝料的財産分与
慰謝料的財産分与とは、相手方の有責な行為により離婚を余儀なくされたような場合、精神的損害の賠償という意味を込めて財産を分与することがあります。慰謝料については、財産分与の中で請求しても、別個に請求してもよいとされています。そこで、調停や離婚協議を成立させる場合には、財産分与に慰謝料を含めているのか明確にしておく必要がある場合もあります。さらに慰謝料等を請求されないために、離婚協議書等には忘れずに清算条項を規定しましょう。
財産分与の対象となる財産と対象外となる財産
財産分与の対象となるのは、夫婦が結婚している間に築いた財産です。ここでは、財産分与の対象となる財産と対象外となる財産について解説します。
(1)財産分与の対象となる財産
財産分与の対象となる財産には、以下のようなものがあります。
①現金・預貯金
家にある現金だけでなく預貯金も対象となり、口座名義が夫婦のどちらのものであろうと対象になります。
②不動産
土地や建物などは財産分与の対象であり、名義人が夫婦のどちらであるかは関係ありません。夫婦が結婚している間に取得した不動産であれば、財産分与の対象になります。
住宅を売却する場合は、住宅ローンを清算して残った金額が財産分与の対象です。ただし、ローンを完済できす債務が残った場合は、夫婦の話し合いにより他の財産で残った債務を返済することがあります。
夫婦のどちらかが不動産を取得する場合には、他方は金銭によりその価値を取得します。
③自動車
自動車も不動産と同じように、名義が夫婦のいずれであっても関係ありません。夫婦が結婚している間に取得した自動車であれば、財産分与の対象になります。
④有価証券
有価証券も名義が夫婦のどちらであるかは問題ではなく、結婚している間に取得していれば財産分与の対象になります。有価証券とは、株式や債券、投資信託、ゴルフ会員権などの金融商品のことです。
⑤金銭的価値のあるもの
絵画や骨とう品、宝石などの金銭的価値があるものは、財産分与の対象です。
⑥家財道具
結婚後に購入した家財道具は夫婦の共有財産であり、財産分与の対象です。
⑦年金
財産分与の対象となるのは厚生年金と共済年金であり、国民年金は対象外です。ただし、年金は結婚していた期間に応じてその記録が分割されます。
⑧退職金
退職金は財産分与の対象ですが、年金と同じように、結婚していた期間に応じて分割されます。
(2)財産分与の対象外となる財産
財産分与の対象外となる財産には、以下のようなものがあります。
①結婚前に築いた財産
プラス財産だけでなく、借金などのマイナス財産も含みます。
②贈与や相続でもらった財産
結婚している間かどうかを問わず、それぞれの親族からの贈与や相続により取得した財産は財産分与の対象外です。
③結婚後に作った負債
ギャンブルや浪費でつくった借金などの負債は、もっぱら自分のために借り入れた個人的な負債であるため、結婚している間のものでも財産分与の対象外となる可能性があります。
④夫婦が別居中に築いた財産
結婚生活を営んでいないので、離婚前でも夫婦が協力して築いた財産ではないため財産分与の対象外となると考えられています。
財産分与の方法は離婚の方法と似ている!?
ここでは財産分与の方法について解説していきますが、離婚するための手続とよく似ています。それでは、順番に従って解説していきましょう。
(1)夫婦間の話し合い
夫婦間の話し合いにより財産分与を取り決めるのが、最も簡単な方法です。当事者が納得すれば自由に決めることができます。
財産分与については、以下の手順で話し合います。
①財産分与の対象となる財産のリストを作る
②リストに上がった財産を夫婦のどちらに分けるかを話し合う
同居している場合は話し合いをしやすいのですが、別居している場合は手紙やメールなどでのやり取りになるでしょう。
③財産分与について合意した内容
これは、文書にしておくのが一般的です。合意のとおりに実行されないこともあるので、公正証書で作成しておくといいでしょう。
※公正証書とは、公証人役場の公証人が作成した法的効力のある文書です。
(2)調停・審判による決着
話し合いで決着しなければ調停をすることになりますが、離婚調停の中で財産分与について話し合うケースと財産分与の請求だけについて話し合うケースがあります。
調停とは家庭裁判所へ申立をして、調停委員が間に入って交渉していく手続です。調停は裁判のように判決を出すわけではないので、当事者が合意しないケースもあります。不調の場合には、審判手続に移行します。財産分与請求権は離婚後2年の除斥期間で消滅しますので、調停・審判手続は、離婚から2年以内に行う必要があります。
(3)離婚訴訟に伴う場合
離婚訴訟に附帯して財産分与の申立てをすることもできます。この場合にも、2年間の除斥期間が適用されます。
まとめ
離婚を検討されている方は、まず財産分与についてしっかりと把握する必要があります。離婚するだけでもエネルギーのいることですが、お金の問題である財産分与はさらに大変です。円満かつスムーズに問題を解決するためには、早めに弁護士へ相談することをお勧めします。何かお悩み事がございましたら、お気軽にご相談ください。
東京大学法学部司法学科卒業。最高裁判所司法研修所修了後、裁判官に任官し、横浜地方裁判所、名古屋地方裁判所家庭裁判所豊橋支部、横浜地方裁判所家庭裁判所川崎支部判事補、東京地方裁判所家庭裁判所八王子支部、浦和家庭裁判所、水戸地方裁判所家庭裁判所土浦支部、静岡地方裁判所浜松支部判事。退官後、弁護士法人はるか栃木支部栃木宇都宮法律事務所勤務。
裁判官時代は、主に家事事件(離婚・財産分与・親権・面会交流・遺産分割・遺言)等を担当した。 専門書の執筆も多く、 古典・小説を愛し、知識も豊富である。 短歌も詠み歌歴30年という趣味も持つ。栃木県弁護士会では総務委員会に加入している。
関連記事
-

親権を勝ち取る!弁護士による3つのアドバイス
離婚と財産分与の方法は似ている この記事では、配偶者との離婚を検討されている方...
2018/12/20
-

夫・妻の不倫が発覚!相手に離婚を切り出す前に弁護士による3つのアドバイス
離婚と財産分与の方法は似ている この記事では、配偶者との離婚を検討されている方...
2018/12/17
-

弁護士が教える養育費について知っておいてほしいこと
離婚と財産分与の方法は似ている この記事では、配偶者との離婚を検討されている方...
2018/11/28
-

熟年離婚しようか考えている方へ。弁護士が教える気を付けるべきこと
離婚と財産分与の方法は似ている この記事では、配偶者との離婚を検討されている方...
2018/11/19
 日本語
日本語  English
English